好きこそ物の上手なれ。
熟達するには、楽しめるようになることが肝心。
楽しく勉強ができるように、
要点をわかりやすく解説するブログです。
この記事では、
令和7年度関西広域連合調理師試験│解答速報│解説をお伝えします。
毎週金曜日に更新される記事をお読みいただき、
一発合格を目指しましょう。
\解答速報の作成依頼を受付中/
解答速報
⚠️ここでお示しする解答は、すきうまブログ独自の見解で作成したもので、各資格試験の主催者とは一切関係ありません。解答速報に関する各資格の主催者へのお問い合わせはご遠慮ください。
⚠️解説から進めていきますので、お急ぎの方はスクロールして解説にお進みください。
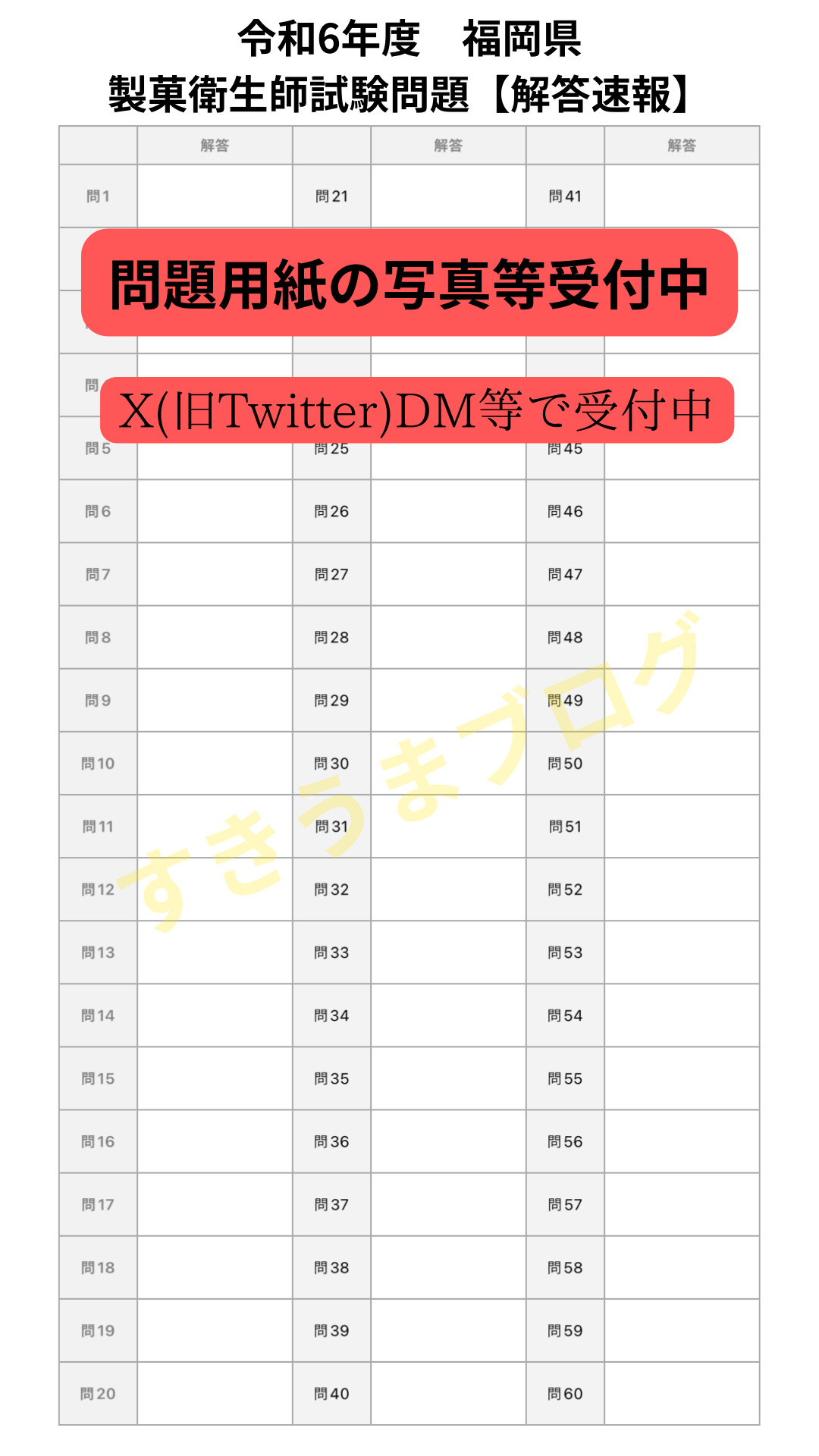
解説
問1
日本国憲法第 25条に関する記述について、(A)及び(B)の中に入れるべき字句の正しい組合せを一つ選べ。
「すべて国民は、健康で文化的な(A)生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び(B)の向上及び増進に努めなければならない。」
(1)最低限度の – 生活水準
(2)基本的 – 生活水準
(3)最低限度の – 公衆衛生
→正しい
(4)基本的 – 公衆衛生
問2
衛生統計に関する記述について、正しいものを一つ選べ。
(1)生後8週未満の死を、乳児死亡という。
生後1年未満
(2)合計特殊出生率とは、15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したものである。
→正しい
(3)令和4年の日本の全人口に対する65歳以上の高齢者人口の割合(高齢化率)は40%を超えている。
→超えていない(令和4年(2022年)の高齢化率は約29.0%)
(4)令和4年の日本の平均寿命は男性、女性ともに85歳を超えている。
→超えていない(女性のみ超えている)
問3
環境衛生に関する記述について、誤っているものの組合せを一つ選べ。
ア)令和2年度から4年度までの3年間において、一般廃棄物(ごみ)の総排出量は増加傾向にある。
→横ばい傾向
イ)空気は、酸素が約78%、窒素が約21%、その他少量の気体で構成されている。
→窒素が約78%、酸素が約21%
ウ)水道法で水道は「水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体」と定義されている。
→正しい
エ)一般廃棄物は、市町村の責任で処理しなければならない。
→正しい
(1)ア、イ
→正しい
(2)ア、ウ
(3)イ、エ
(4)ウ、エ
問4
公害に関する記述について、正しいものを一つ選べ。
(1)水質汚濁の原因として、一般家庭から出る生活排水が挙げられる。
→工場排水
(2)二酸化炭素は、代表的な大気汚染物質である。
→二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質など
(3)水俣病は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)が原因である。
→メチル水銀
(4)PM2.5は、主に泌尿器系に影響を与える。
→呼吸器・循環器系
問5
感染症に関する記述について、正しいものを一つ選べ。
(1)感染の発生には、感染源、感染経路、感染期間の3つの条件が必要である。
→感受性宿主
(2)感染症の感染源対策として、予防接種が行われる。
→「宿主の抵抗力を高める」
(3)病気の症状は示さないが、体内に病原体を持っていることがある。
→正しい
(4)日本では、感染症法により、検疫感染症が指定されている。
→検疫法
問6
感染症の疾患名と感染経路の組合せで、誤っているものを一つ選べ。
(1)赤痢 – 経口感染
(2)インフルエンザ – 飛沫感染
(3)日本脳炎 – 空気感染
→蚊媒介感染
(3)梅毒 – 接触感染
問7
令和6年時点において、感染症の類型と感染症名の組合せで、誤っているものを一つ選べ。
(1) 1類感染症 – エボラ出血熱
(2) 2類感染症 – 新型コロナウイルス感染症
→5類(令和5年5月8日以降、2類感染症ではなく5類感染症に分類されている)
(3) 3類感染症 - コレラ
(4) 5類感染症 – 麻しん
問8
生活習慣病に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
(1)生活習慣病には、がん、結核、糖尿病がある。
→結核は生活習慣病ではなく感染症である
(2)生活習慣病の予防には、食生活、運動、喫煙、飲酒などの生活習慣の見直しが有効である。
(3)メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の診断に用いられている項目の一つに、腹囲がある。
(4)高血圧は、脳血管疾患、心疾患等の大きな要因になる。
問9
産業保健関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
(1)労働衛生に関する法律として、労働基準法と労働安全衛生法がある。
(2)職場の健康づくりにおいて、労働者のストレスチェックが義務化されている。
(3)作業環境により、熱中症、職業性難聴、白ろう病などの職業病を引き起こすことがある。
(4)事業者は、労働安全衛生法に基づき、有害業務に従事する労働者に対して特定健康診査を実施しなければならない。
→特殊健康診断
(「特定健康診査」は主に40歳以上の被保険者を対象とした医療保険制度上の健診であり、労働安全衛生法に基づくものではない。)
食品衛生学
問10
一般的にこうじかびを利用して製造する食品として、正しいものを一つ選べ。
(1)ビール
→酵母菌
(2)清酒
→正しい
(3)ワイン
→酵母菌
(4)糸引き納豆
→納豆菌
問11
野菜類に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
(1)水分含量は、一般的に90%前後のものが多い。
(2)春キャベツは、冬キャベツよりも肉質が柔らかめである。
(3)ねぎの旬は、夏である。
→冬
(4)ほうれんそうの東洋種は、西洋種よりもアクが少ない。
問12
肉類に関する記述として、正しいものを一つ選べ。
(1)必須アミノ酸含量が少ない。
→多い
(2)豚肉は、ビタミンB、合量が多い。
→正しい
(3)子羊肉をマトンという。
→成羊肉(子羊肉はラム)
(4)食肉処理(と殺)直後が、一番柔らかく、うま味が強い。
→硬く、熟成を経て柔らかくなり、うま味も増す
問13
油脂類に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
(1)バターは、ビタミンAを含まない。
→豊富に含む
(2)オリーブ油には、カロテンが含まれる。
(3)オリーブ油には、オレイン酸が多く含まれる。
(4)サラダ油は、脱ろう(ウィンタリング)処理後に製品化される。
問14
きのこ類に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
(1)近年、血中コレステロールの低下作用が注目されている。
(2)代表的なうま味成分は、イノシン酸である。
→グアニル酸
(3)国内で消費量が多いものは、人工栽培が可能なものである。
(4)しいたけを天日干しすると、ビタミンD2が増える。
問15
日本酒の醸造に使用される代表的な米の品種として、最も適切なものを一つ選べ。
(1)コシヒカリ
(2)ひとめぼれ
(3)日本晴
(4)山田錦
→正しい(「酒米の王様」とも呼ばれている)
栄養学
問16
炭水化物に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
(1)水溶性食物繊維には、人の血中コレステロール低下作用がある。
(2)多糖類のグリコーゲンは、肝臓、筋肉中に存在する。
(3)麦芽糖(マルトース)は、多糖類に分類される。
→二糖類
(4)ブドウ糖(グルコース)は、単糖類に分類される。
問17
たんぱく質とアミノ酸に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
(1)たんぱく質は、1gにつき約4kcalのエネルギーをもつ。
(2)アミノ酸は、全て人の体内で合成される。
→必須アミノ酸は体内で合成されない
(3)たんぱく質やアミノ酸を特徴付けているアミノ基は、必ず窒素を含む。
(4)たんぱく質は、筋肉、血液、皮膚、爪などの主要な構成成分である。
問18
脂質に関する記述について、正しいものを一つ選べ。
(1)中性脂肪は、ステロイドホルモンや胆汁酸、生体膜の構成成分である。
→コレステロール
(2)コレステロールは、肝臓で合成される。
→正しい
(3)水溶性ビタミンの腸管吸収を、促進する作用がある。
→脂溶性ビタミン
(4)エイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)は、牛脂に多く含まれる。
→魚油
問19
ビタミンとその働きの組合せとして、正しいものを一つ選べ。
(ア) ビタミンB1は、主にたんぱく質の代謝(エネルギー化)の補酵素として働く。
→糖質
イ)ビタミンAは、脂質の代謝に補酵素として関わる。
→関与していない
ウ)ビタミンKは、血液凝固因子の合成に必要である。
→正しい
工)ビタミンDは、腸管からのカルシウムとリンの吸収を促進する。
→正しい
(1)ア、イ
(2)ア、ウ
(3)イ、工
(4)ウ、エ
→正しい
問20
骨粗鬆症とその予防に関する記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組合せを一つ選べ。
骨粗鬆症の発症は高齢の(A)に多い。予防として、子どものときからバランスのよい食事、栄養素では特に(B)を十分に摂り、適度に日光に当たり、よく進動をする。(B)を多く含む食品として、(C)や小魚、海藻などがある。
A B C
(1) 男性–カリウム-牛乳・乳製品
(2) 男性-カルシウム-野菜・果物
(3) 女性-カルシウム-牛乳・乳製品
→正しい
(4) 女性-カリウム-野菜・果物
問21
消化酵素の働きに関する記述について、正しいものを一つ選べ。
(1)アミラーゼは、たんぱく質をポリペプチドに分解する。
→でんぷん(多糖類)をマルトース(麦芽糖)
(2)リパーゼは、中性脂肪を脂肪酸とモノグリセリドに分解する。
→正しい
(3)ラクターゼは、麦芽糖をブドウ糖に分解する。
→乳糖(ラクトース)をブドウ糖とガラクトース
(4)ペプシンは、でん粉を麦芽糖に分解する。
→アミラーゼ
問22
妊娠期・授乳期の栄養に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
(1)妊娠中は、貧血になりやすい。
(2)妊娠中は、カルシウム吸収率が著しく低下する。
→高まる
(3)妊娠期は、妊娠高血圧症候群になりやすい。
(4)授乳中は非妊娠期・非授乳期よりも多くの栄養素が必要となる。
問23
ホルモンに関する記述について、正しいものを一つ選べ。
(1)インスリンは、肝臓のグリコーゲンの分解を促進し血糖を上昇させる。
→低下
(2)グルカゴンは、血中のグルコース(ブドウ糖)を筋肉、脂肪組織、肝臓に取り込み血糖を低下させる。
→上昇
(3)アドレナリンは、脳下垂体から分泌され、血圧を低下させる。
→上昇
(4)ガストリンは、胃幽門のG細胞から分泌され、胃酸分泌を促進する。
→正しい
問24
基機代謝量(生きていくために最低限必要なエネルギー消費量)に関する記について、正しいものを一つ選べ。
(1)基礎代謝量は、除脂肪体重(骨格筋や内臓器官など)に反比例する。
→比例
(2)同年齢では、男性より女性の方が基礎代謝量が大きい。
→小さい
(3)体温が上昇すると、基礎代謝量が低くなる。
→高く
(4)同じ体重では、体表面積が大きい(身長が高い)方が、基礎代謝量が大きい。
→正しい
問25
黄色ブドウ球菌に関する記述について、正しいものを一つ選べ。
(1)食中毒の主な症状は吐き気、嘔吐などである。
→正しい
(2)食中毒の潜伏期間は、平均24~48時間である。
→30分〜6時間程度
(3)エンテロトキシンという熱に弱い毒素を産生する。
→強い
(4)海水中に存在し、3%程度の食塩濃度の環境で最も増殖する。
→人や動物の皮膚や粘膜に常在
問26
カンビロバクター食中毒に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
(1)主な症状は、下痢、腹痛、発熱である。
(2)数百個程度の菌でも発症することがある。
(3)潜伏期間は2~5時間である。
→2〜5日
(4)鶏の刺身、加熱不足の焼き鳥などによる感染が多い。
問27
食中毒の病因物質と主な原因食品の組合せとして、正しいものを一つ選べ。
(1)ボツリヌス菌 - 卵焼き
→缶詰、ビン詰め、真空パック食品、発酵食品
(2)セレウス菌 - 米飯
→正しい
(3)ヒスタミン – ビーフシチュー
→青魚
(4)サルコシスティス・フェアリー – ヒラメの刺身
→クドア
問28
ノロウイルス食中毒とその予防に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
(1)主な症状は、吐き気、職性、腹痛、下痢、発熱である。
(2)潜伏時間は、通常 24~48時間である。
(3)70%エタノールにより、ノロウイルスは死滅する。
→次亜塩素酸ナトリウムが有効
(4)人の体内に入ったノロウイルスは、小腸で増殖する。
問29
植物性自然毒による食中毒の原因植物と有毒物質の組合せとして、誤っているものを一つ選べ。
(1)イヌサフラン – コルヒチン
(2) 青梅 – アミグダリン
(3) ジャガイモ – ソラニン
(4)チョウセンアサガオ – アコニチン
→アトロピン
問30
アニサキスに関する記述について、正しいものを一つ選べ。
(1)アニサキス幼虫は体長約10μm(マイクロメートル)と小さいため、肉眼で確認することができない。
→2〜3cm
(2)酢によって死滅する。
→しない
(3)−20℃以下で24時間以上凍結することにより、死滅する。
→正しい
(4)食中毒の代表的な症状は、肝機能障害、血療である。
→腹痛、吐き気、嘔吐
問31
食品添加物の種類と物質名の組合せで、正しいものを一つ選べ。
(1)甘味料 – 安息香酸
→保存料
(2)保存料 – スクラロース
→甘味料
(3)発色剤 – 次亜硫酸ナトリウム
→漂白剤、酸化防止剤
(4)防かび剤 – ジフェニル
→正しい
問32
食品中の汚染物質及び残留物に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
(1)米ぬか油による油症(「カネミ油症」)事件の原因は、製造過程で混入したメチル水銀である。
→ダイオキシン類
(2)イタイイタイ病の原因であるカドミウムは、食品衛生法で玄米及び精白米の基準値が定められている。
(3)代表的なカビ毒であるアフラトキシンには、発がん性がある。
(4)ポジティブリスト制度とは、原則として全ての農薬の残留を禁止し、「一定量以下の残留を認めるもの」のみを一覧表にして示す方式である。
問33
食品中の異物に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
(1)異物の混入により人の健康を損なうおそれがある食品を製造することは、食品衛生法において禁止されている。
(2)動物性異物とは、昆虫の破片、ねずみのふん、寄生虫の卵などをいう。
(3)植物性異物とは、紙片、糸くず、人毛などをいう。
→人毛は動物性異物
(4)鉱物性異物とは、土砂、ガラス片、金属片などをいう。
問34
水分活性を低下させることにより、微生物が発育・増殖しにくい状態にして保存する方法の組合せとして、正しいものを一つ選べ。
ア) 低温貯蔵法
イ) 乾燥法
ウ)砂糖漬け法
エ)加圧加熱殺菌法(レトルト殺菌法)
(1)ア、ウ
(2)ア、エ
(3)イ、ウ
→正しい
(4)イ、エ
問35
消毒に関する記述について、正しいものを一つ選べ。
(1)逆性石けんは、洗浄力は非常に強いが、殺菌力は弱い。
→ほとんどない、強い
(2)紫外線殺菌灯による消毒は、照射表面のみならず、影の部分にも効果がある。
→ない
(3)アルコールによる消毒は、濃度が約70%の溶液より100%のものの方が強い効果を持つ。
→低い
(4)次亜塩素酸ナトリウム溶液は、時間の経過や日光によって効力が減少する。
→正しい
問36
施設、設備及び器具類の衛生管理に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
(1)食肉類と魚介類は、もともと食中毒菌に汚染されているため、まな板は同じものを使用する。
→まな板や包丁は用途別・食品別に専用のものを使用することが衛生管理の基本
(2)施設とその周辺を清潔に保ち、そ族・衛生害虫の繁殖場所を排除するとともに、記録を1年間保管する。
(3)冷蔵庫内は食材ごとに区分し、交差汚染が起こらないようにする。
(4)原材料の入っていたダンボール箱を食品保管庫に持ち込むと汚染が広がるおそれがあるため、専用の容器に移し替える。
問37
大量調理施設生管理マニュアルに関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
(1)同一メニューを1回 300食以上又は1日750食以上を提供する調理施設に適用される。
(2)器具、容器等の使用後は、流水で洗浄し、75°C、1分間以上の加熱又はこれと同等の効果を有する方法で殺菌する。
→80°C、5分以上
(3)検食は、食品ごとに 50g程度ずつ清潔な容器に入れ密封し、一20°C以下で2週間以上保存する。
(4)食品の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面から60cm以上の場所で行う。
問38
HACCPに関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
(1)原則として、全ての食品等事業者に、「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求められる。
(2)「HACCPに沿った衛生管理」は、「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に分けられる。
(3)「HACCPに基づく衛生管理」では、製品の安全性の保証に最も重要な事項は、最終製品の試験結果である。
→製造工程中の危害要因の管理(特に重要管理点:CCPの管理)
(4)「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」では、衛生管理計画を作成し、それに基づき実施した衛生管理の結果を記録する。
問39
HACCPの7原則として、()の中に入れるべき字句の正しい組合せを一つ選べ。
原則1 (A)
原則2 重要管理点の決定
原則3 (B)
原則4 モニタリング方法の設定
原則5 改善措置の設定
原則6 検証方法の設定
原則7 記録と保存手順の設定
A B
(1)危害要因の分析 – 衛生教育の実施
(2危険要因の分析 – 管理基準の設定
→正しい
(3)衛生委員会の設置 – 衛生教育の実施
(4)衛生委員会の設置 – 管理基準の設定
調理理論
問40
ゆで物への添加材料に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
(1)青菜を茹でるときは、食塩を加えるとクロロフィルが安定化し、色がきれいに仕上がる。
(2)たけのこを茹でるときは、米ぬかを加えると味もよく、柔らかくなる。
(3)わらび、ぜんまいを茹でるときは、酢を加えると酢の酸により機維が散化する。
→重曹や木灰のアルカリ性を加えることで繊維が柔らかくなる
(4)やつがしらを茹でるときは、みょうばんを加えると細胞膜のペクチン質が不溶化し、煮崩れを防ぐことができる。
問41
蒸す調理操作に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
(1)材料の特徴を失わずに中心部まで加熱するのに適した調理操作である。
(2)色、味、香りを保つと同時に、生臭みも完全に取り除くことが期待でき、青魚の調理にも適している。
(3)糯米は、でん粉の糊化に多量の水を必要とするため、途中で何度も振り水をしなければならない。
→事前にしっかり浸水させたうえで水気を切り、蒸し器で蒸す
(4)茶碗蒸しは、100°Cで調理すると、すが立ってしまうので、85~90°Cで加熱するのが好ましい。
問42
色素に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
(1)クロロフィルは、野菜に含まれる緑色の脂溶性色素である。
(2)カロテノイドは、野菜や果物に含まれる黄~赤色系の脂溶性色素である。
(3)中華めんが黄色いのは、小麦粉のフラボノイドがアルカリ性のかん水で黄色くなるからである。
(4)肉や赤身の魚の色は、ペクチンによるものである。
→ミオグロビン
問43
調理による褐変に関する記述について、()の中に入れるべき字句として、正しいものを一つ選べ。
たんぱく質やアミノ酸とブドウ糖などの糖類が一緒になって強く加熱されると
( )が起こり変する。
(1)酵素反応
(2)アミノカルボニル反応
→正しい
(3)糊化
(4)乳化
問44
油脂の劣化・変敗の防止に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
(1)空気になるべくさらす。
→触れさせない
(2)長時間の加熱をできるだけ避ける。
(3)不純物を混ぜない。
(4)直射日光に当てない。
問45
米に関する記述として、正しいものを一つ選べ。
(1)無洗米は、ぬかを除去した米で、研ぎ洗いを必要としない。
→正しい
(2)アルファ化米は、精米にビタミンB1、ビタミンB2などの栄養素を添加したものである。
→強化米
(3)発芽玄米は、玄米と比べて長時間の浸水を必要とする。
→通常の玄米より浸水時間は短いか同等
(4)強化米は、炊飯で米を糊化させた後に乾燥させたもので、水や湯を加えると米飯として食べることができる。
→アルファ化米
問46
豆類の調理に関する記述として、正しいものを一つ選べ。
(1)大豆は、洗ったらすぐに火にかけて、初めから緩やかに加熱して表皮を柔らかくする。
→十分な時間(6~10時間程度)水に浸してから
(2)煮豆を作るときは、調理中に調味料を一度に加え直ちに煮ると、しわが寄りにくい。
→やすい
(3)煮豆を作るときにみょうばんを加えると、柔らかく、しわのない状態に仕上がる。
→固くなる
(4)黒豆を煮るとき、古釘を入れると鮮やかになる。
→正しい
問47
魚介類の調理に関する記述として、正しいものを一つ選べ。
(1)炭火を用いて、魚を焼く際の火加減は、強火の遠火にする。
→正しい
(2)煮魚を作る際は、十分にうま味を出すために、必ず煮汁が煮立つ前に、魚を入れる。
→煮立った煮汁に
(3)赤身魚は加熱すると固くなるが、白身魚ほど固くならない。
→なりやすい
(4)酢じめは、魚肉を食酢に浸して締めた後、食塩で肉質を引き締める方法である。
→まず食塩で魚を締めた後、酢に漬ける工程(塩→酢)
問48
牛乳、乳製品止関する記述として、正しいものを一つ選べ。
(1)レバーのにおいを除きたいときは、牛乳に浸すと牛乳の成分がにおいを吸着する。
→正しい
(2)カスタードブディングに牛乳を加えると、牛乳のカルシウムによって卵の熱凝固が抑制される。
→促進
(3)ヨーグルトは、乳酸発酵により乳脂肪を凝固させたものである。
→たんぱく質
(4)折込パイ生地は、バターのクリーミング性を利用している。
→可塑性
問49
みりん、酒に関する記述として、正しいものを一つ選べ。
(1)みりんは、粳米に米麹、焼酎もしくは醸造アルコールを加え熟成させたものである。
→もち米
(2)みりん風調味料は、アルコールが11~14%含まれる酒類調味料である。
→本みりん
(3)みりんの甘みは、主にペプチドによるものである。
→糖
(4)料理酒は、日本酒の製造過程で塩などを加えた調味料である。
→正しい
問50
新調理システムに関する記述として、正しいものを一つ選べ。
(1)クックチルシステムにおける急速冷却とは、30分間以内に中心温度3℃以下まで冷却を行うことを指す。
→加熱調理から30分以内に冷却を開始し、90分以内に中心温度3℃以下まで下げる
(2)クックフリーズシステムとは、クックチルシステムの急速冷却の工程から、さらに冷却を続け、最終的な品温を一10°C以下としたものである。
→−18°C
(3)真空調理法とは、食材を調味液と一緒に袋に詰めて真空包装し、48~75°Cの低温で一定時間加熱する調理法である。
→正しい
(4)冷却または冷凍されたものの再加熱は、ノロウイルス汚染のおそれがある食品を除き、中心温度75°C以上で1分間以上とされる。
→ノロウイルス汚染の有無に関わらず
問51
炒める調理操作に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
(1)間接焼きの一つである。
(2)加熱温度は、一般的に150~200°Cくらいで、比較的高温である。
(3)幅広い食材に利用できる。
(4)高温短時間加熱のため、栄養素の損失が煮物などに比べて多い。
→少ない
問52
藻類に関する記述として、正しいものを一つ選べ。
(1)あまのり(あさくさのり)は、緑藻類に分類される。
→紅藻類
(2)藻類は、色素成分としてフラボノイドとアントシアニンなどを含み、含量の差によって色調が決まる。
→クロロフィル(緑色)、フィコビリン(赤系、青系)、カロテノイド(黄~橙)
(3)藻類には、うま味成分であるグルタミン酸、アスパラギン酸などが含まれる。
→正しい
(4)ひじきは、加熱前は緑色であるが、短時間の加熱によって黒色になる。
→誤りである
問53
卵白の起泡性に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
(1)卵白が水様化している卵は、泡立てやすい。
→泡立ちにくい
(2)泡立てる卵液の温度が高いほうが、起泡性がよい。
(3)卵白を泡立てるボウルに油脂が付着していると、撹拌しても泡立ちにくいことがある。
(4)泡立てる卵白に砂糖を加えると泡立ちにくくなり、泡の安定性も低下する。
問54
バターの特徴に関する記述として、正しいものを一つ選べ。
(1)ビタミンCを多く含んでいる。
→ビタミンA
(2)日本では、主に発酵バターが使われてる。
→無発酵バター
(3)乳脂肪を凝集させた油中水滴型エマルションである。
→正しい
(4)脂質は、約60%である。
→80%
問55
ゼラチンに関する記述について、正しいものの組合せを一つ選べ。
ア) 紅藻類のてんぐさやおごのりを主原料とする。
→寒天に関する記述である
イ)ゼラチンゲルの凝固温度は、寒天ゲルより高い。
→低い
ウ)たんぱく質分解酵素を含む食品を加えてゼリーを作ると、固まりにくくなる。
→正しい
エ)砂糖を加えてゼリーを作ると、固まりやすくなる。
→正しい
(1)ア、イ
(2)ア、ウ
(3)イ、エ
(4)ウ、エ
→正しい
問56
冷凍室の食品保存に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
(1)すでに凍っているものと、新たに冷凍しようとするものを重ねて入れない。
(2)すき間なく詰めて入れると、ドアを開けたときに外の暖かい空気が広く当たり、冷凍室内の温度が上昇しやすい。
→冷気が逃げにくく、開閉時の温度変化が少なく冷凍室内の温度が上昇しやすい
(3)野菜類は、酵素が働かないように、ブランチング(湯通し)してから冷凍する。
(4)食品を冷凍用に包装するときは、空間がないよう、袋を密着させる。
食文化概論
問57
日本の行事とその行事食との組合せについて、誤っているものを一つ選べ。
(1)端午の節句 -ちまき、かしわ餅
(2) 正月 – おせち料理、雑煮
(3)重陽の節句 – 菊酒
(4) 上巳の節句 – 七草がゆ
→ちらし寿司
問58
揚子江上流地帯の「四川料理」の代表的な料理として、正しいものを一つ選べ。
(1)水餃子
→江南、上海エリア
(2)麻婆豆腐
→正しい
(3)酢豚
→広東料理
(4)小籠包
→江南、上海エリア
問59
茶道と結びついた料理で、濃い抹茶をおいしく飲むために出される(食べられる)空腹しのぎ程度の軽い食事として、正しいものを一つ選べ。
(1)精進料理
(2)会席料理
(3)普茶料理
(4)懐石料理
→正しい
問60
食器・容器に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
(1)銀食器は、強い酸には弱いため、手入れには注意が必要である。
(2)木製品に漆を塗った漆器は、傷が付きやすいが衝撃には強い。
→つきにくい、弱い
(3)陶器は、素地に釉薬をかけて焼いたものである。
(4)ソーダガラスは、コップなどの一般的な食器に多く使われている。
次回予告
この記事では、
令和7年度関西広域連合調理師試験│解答速報│解説をお伝えしました。
次回更新時も勉強される方は、
- こちらのページをブックマーク
- ブログ名【すきうまブログ】を覚えて、次回検索
どちらかをおすすめします。
初めて当サイトをご覧になった方は、調理師の試験対策として、暗記すべき要点をまとめた記事もありますので、下記の記事から順にご覧ください。
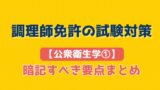
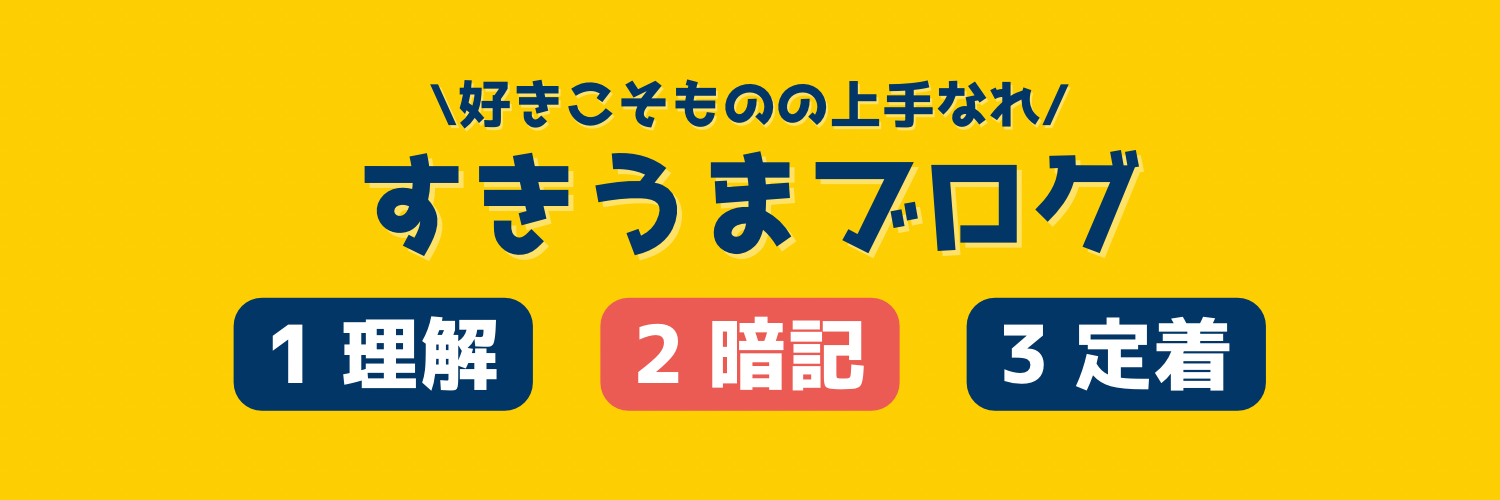
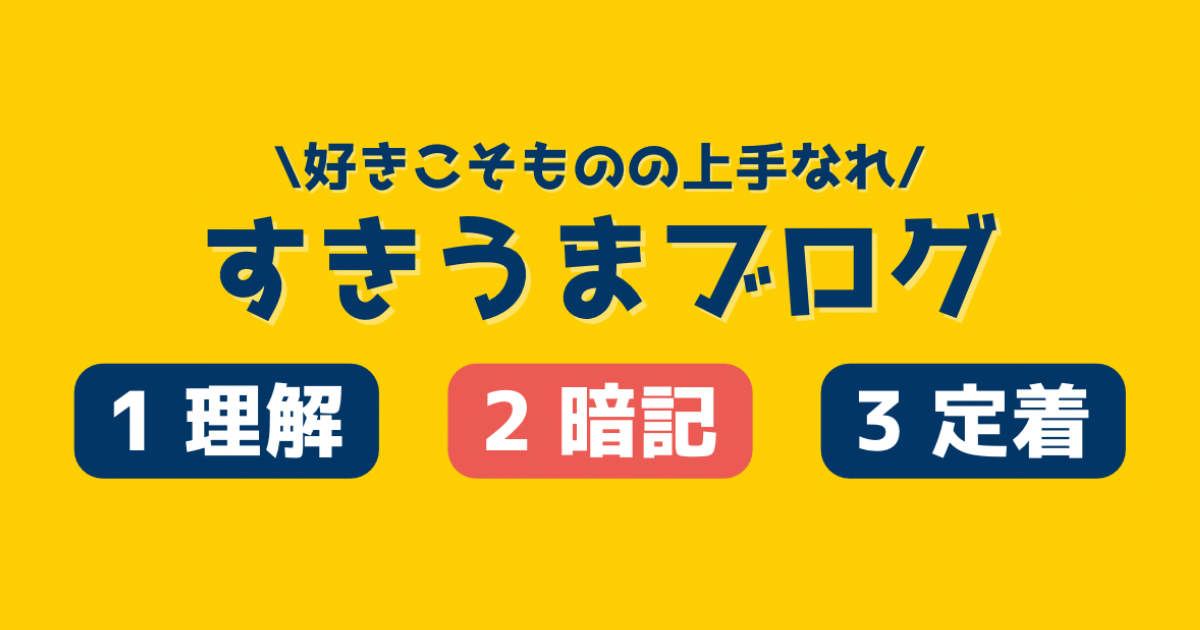
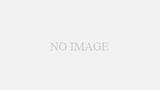
コメント
本日行われた、神奈川県の調理師試験も速報は出ますでしょうか?お待ちしております!よろしくお願いいたします!
試験お疲れ様でした!
問題用紙の提供を受けていますので、進めていきます♪
子育ての合間になりますので、途切れ途切れになると思いますが、更新していきますので、しばらくお待ちくださいm(_ _)m
令和7年の調理師試験解答は
いつごろ全部公表しますか?
よろしくお願いします。
試験お疲れ様でした!
全問公開まで遅れてしまってすみません。
先ほど60問目まで更新できましたので、ぜひご確認ください♪
お待たせしました!